介護の基礎知識
【高齢者向け】楽しくできる脳トレレクリエーション・ゲーム16選
- 公開日:2025年04月23日
- 更新日:2025年08月12日

年齢を重ねるにつれて、認知機能が低下し、認知症になるリスクも増加していきます。
認知症防止のためにも楽しく続けられる脳トレが効果的です。本記事では、楽しく脳トレができるレクリエーション・ゲームを16個厳選しました。簡単に取り入れられて、誰でも楽しめる活動ばかりなので、介護施設や家庭でのケアに役立てていただけます。
これらのレクリエーションは、記憶力や思考力の向上だけでなく、コミュニケーションの促進や心身のリラックス効果も期待できます。ぜひ、日常的に取り入れて、脳の健康をサポートしていきましょう!
脳トレレクリエーション・ゲーム16選

制限付きしりとり
制限付きしりとりは、通常のしりとりに特定のルールを加えた言葉遊びゲームです。ルールがあることで、言葉を思い出す力や発想力が鍛えられ、脳の活性化に効果的です。
■やり方
①職員が「どんな制限をつけるか」を決めます。(制限の例:5文字の単語、カタカナの言葉、食べ物の名前、3文字以上の単語など)
②制限を守りながらしりとりをします。
古今東西ゲーム
古今東西ゲームは、特定のテーマに沿った言葉を次々に答えていくシンプルなゲーム脳トレです。制限時間やルールを工夫することで、発想力や記憶力を刺激しながら盛り上がることができます。
■やり方
① 職員がお題を決めます。お題は、利用者がイメージしやすいものにすると楽しさが増します。(例:フルーツの名前、昭和の歌手、映画のタイトル)
②1人目から順にお題の言葉を発表していきます。次の人は、前の人と同じ単語を言わないように注意しましょう。
犬・猫トレーニング

犬・猫トレーニングは、職員が言った動物の名前に対応する鳴き声を利用者が答えるゲームです。シンプルなルールながら、注意力や瞬発力を鍛えられ、脳の活性化に効果的です。
■やり方
①職員が「犬」や「猫」など、動物の名前をはっきりと伝えます。
②利用者は、その動物に合った鳴き声を答えます。(例:犬→ワンワン、猫→ニャー、牛→モーモー、カエル→ゲロゲロ、ニワトリ→コケコッコー)
インタビュー暗記ゲーム
「暗記ゲーム」は、利用者の「好きなもの」を聞いたあと、その内容を記憶して当てるゲームです。「全員分の好きなものを暗記できているか?」を確認し、正解の数の多いチームが勝利です。人の話をしっかり聞くことで記憶力や集中力を鍛えられ、インタビューによって思考力やコミュニケーション力の向上にもつながります。楽しい会話が生まれ、交流を深めるきっかけにもなります。
■準備するもの
- メモ用紙やホワイトボード(質問内容や回答を記録するため)
- 時計やタイマー(インタビューの時間管理用)
- 参加者全員分の「テーマ」を決めたリスト(予め決めておく)
■やり方
①利用者を複数のチームに分けます。1チーム3〜5人が理想です。
②職員が事前に決めたテーマに基づいて、各チームのメンバーに対して質問をします。質問は1つずつ行い、利用者が答える時間を取ります。職員が回答をメモし、利用者の答えを記録します。(質問例:好きな色、好きな食べ物、好きな映画、好きな場所、思い出の旅行先 など)
③チームメンバー同士で、テーマに関連した質問をしてインタビューを行う時間を設けます。
④インタビューが終わった後、職員が「最初にメンバーが答えた内容を記憶しているか?」を確認します。各チームのメンバーは、他のメンバーの最初の答えを1人ずつ発表し、正解の数が多いチームが勝ちです。
■ポイント
- 各チームが交互に答える形式にすると、より緊張感が高まります。
- テーマをより感情に関連づけると、答えが心に残りやすくなります。例えば、「最近感動した出来事は?」や「子どもの頃、一番楽しかったことは?」などを質問します。
歌詞リレー

歌詞リレーは、利用者が順番に歌を歌い、歌詞をつないでいくゲームです。歌詞を覚える記憶力や、歌に合わせて音楽を楽しむ感覚を養うことができ、集団で行うことでコミュニケーション力や協力精神も高まります。「昭和のヒット曲」や「季節に関連する歌」、「動物に関する歌」など、特定のテーマに沿って歌を選ぶことでより盛り上がります。
■準備するもの
- 歌詞を覚えるための歌本や歌詞カード(必要に応じて)
- マイク(もしあれば)
- 音楽プレーヤーや簡易的な音響設備(オプション)
■やり方
①事前に、歌う曲をいくつか決めておきます。利用者が馴染みのある歌や、覚えるのが簡単な童話など、みんなで楽しめる歌を選ぶと良いでしょう。
②最初の利用者が歌い出し、次の利用者がその歌詞の続きを歌います。リレーは順番に行い、利用者全員が歌うまで続けます。歌詞の間違いや詰まった部分があれば、他の利用者が助け舟を出し合うことで、和気あいあいと進行します。
早口言葉
早口言葉は記憶力や集中力を鍛える言葉遊びゲームです。例えば、「寿限無(じゅげむ)」を使った早口言葉は、楽しみながら発声練習・口腔機能の維持が行えます。
<寿限無で登場する男の子の名前>
じゅげむじゅげむ ごこうのすりきれ かいじゃりすいぎょのすいぎょうまつ うんらいまつ ふうらいまつ くうねるところにすむところ やぶらこうじのぶらこうじ パイポパイポ パイポのシューリンガン シューリンガンのグーリンダイ グーリンダイのポンポコピーの ポンポコナーの ちょうきゅうめいのちょうすけ
まずはゆっくりと読み上げ、徐々にスピードアップしながら挑戦することで、口の運動や発声練習にもつながります。
■準備するもの
- 「寿限無」の全文を書いた紙(大きくて見やすい文字で)
- ホワイトボードやフリップ(全員が見られるようにする)
- タイマー(あれば)
■やり方
①簡単な発声練習からスタートします。
②「寿限無って何?」という人のために、簡単に内容を説明します。寿限無は「江戸時代の落語で、縁起のいい言葉をたくさん集めた名前のお話」です。
③「寿限無」を全員でゆっくり読み上げます。
④読み上げるスピードを徐々に上げ、無理のない範囲でタイムチャレンジを行います。
クイズ
クイズは手軽にできる脳トレです。出題の仕方によって様々にアレンジでき、飽きずに取り組めます。アレンジ例は以下の通りです。
■笑いと会話を引き出す「シルバー川柳クイズ」
ユーモアたっぷりの「シルバー川柳」は、施設の雰囲気を和ませるのに最適なゲームです。
<クイズ形式の例>
- 「実は俺 点滴、シップの ○○○」(正解:二刀流)
- 「○○○ 持続可能か 聞くな孫」(正解:お年玉)
- 「兄弟で ひとり○○○の 変異株」(正解:薄毛)
ホワイトボードに川柳の一部を空欄にして出題すると、利用者さんが自由に答えを考えられるので、自然と笑顔が生まれやすくなります。利用者さんの興味に合わせて川柳を選び、クイズは穴埋めの箇所を工夫して難易度を調整しましょう。
■今日は何の日?「365日クイズ」
「365日クイズ」は、「今日は何の日?」に関連したクイズを出題します。単に話題を紹介するだけでなく、利用者さんが答えを考える時間を設けることで、脳の活性化にもつながります。
例えば、10月10日は「スポーツの日」。この日は日本の体育振興を目的として制定された記念日です。この話題に関連して、「スポーツの起源はどこの国?」や「オリンピックで最も多くのメダルを獲得した国は?」など、運動やスポーツに関するクイズを出すと、スポーツ好きの方でも、あまり詳しくない方でも楽しめます。
■クイズで食事を楽しみに「食材でメニュー当て」
その日の食材をヒントに、どんな料理が出るかを当てるクイズです。食欲が落ちている方でも、ゲーム感覚で楽しめるので、食事への関心が高まりやすくなります。
<メニュー当てクイズの例>
- 豚肉、じゃがいも、玉ねぎ、糸こんにゃく、にんじん → 肉じゃが
- とうもろこし、玉ねぎ、牛乳、バター、パセリ → コーンポタージュ
- 鶏肉、ごぼう、しいたけ、こんにゃく、お米 → 五目ごはん
難しい場合は「おふくろの味」「甘くてとろっとしている」「もちもちした食感」などのヒントを加えると、より答えやすくなります。
■その他のクイズ
その他のクイズのアイデア例は以下の通りです。
- 「漢字問題」:難読漢字や熟語の読みを当てるクイズ
- 「都道府県当てクイズ」:ヒントから都道府県名を当てるゲーム
- 「歌クイズ」:歌の一節から曲名を当てる問題
野菜の重さ当て

「野菜の重さ当て」は、さまざまな野菜を見たり触ったりしながら「重い順」に並べるゲームです。思考力や集中力が鍛えられ、視覚・触覚・嗅覚などの五感を刺激するため、脳の活性化にも役立ちます。
■準備するもの
- さまざまな重さの野菜(例:にんじん、じゃがいも、玉ねぎ、キャベツ、かぼちゃなど)
- 計り(キッチンスケールなど)
- ホワイトボードや得点表(得点を記録する場合)
- テーブル(参加者が見やすく、触りやすい位置に並べる)
■やり方
①個人戦・グループ戦どちらでも可能です。グループ3〜5人にすると、相談や話し合いが活発になり盛り上がります。
②テーブルの上に数種類の野菜を並べます。野菜の数は4〜6種類ほどが最適です。多すぎると難易度が上がるので、利用者の様子に合わせて調整しましょう。
③利用者は野菜を1つずつ手に取り、重さを予想しながら「重い順」に並べ替えます。野菜は「持つ」「見る」「匂いを嗅ぐ」ことができますが、振ったり投げたりするのはNGです。
④並び替えが終わったら、1つずつ計りで重さを量り、正しい順番を確認し、正解発表を行います。実際の重さと照らし合わせ、最も近い予想を立てた人(チーム)が勝利です。
■ポイント
- 30秒や1分など、制限時間を設けるとスリルが増します。
- 「この野菜は何の栄養が豊富?」「旬の季節は?」など、野菜に関するクイズをプラスすると学びの要素が加わります。
- 目隠しをして「触覚だけ」で重さを予想するルールにすると、より五感が刺激されます。
- 持ったときの重さに意外性があるものを選ぶと、よりクイズが面白くなります。(軽めの野菜:レタス、ピーマン、トマト・重めの野菜:キャベツ、かぼちゃ、大根)
連想衰弱
連想衰弱は、言葉の連想力やチームワークが問われるゲームです。シンプルなルールながら、ひらめきやコミュニケーションが鍛えられ、幅広い世代に楽しんでもらえるレクリエーションです。
■準備するもの
- お題カード(お題の言葉を書いたカード)
- ヒントカード(お題を連想させる言葉を書いたカード)
- ペンと紙(得点を記録する場合)
■やり方
①職員が「お題」を決め、利用者には内緒にします。お題は身近なものや簡単な言葉がオススメです。(例:ポスト、りんご、時計、傘など)
②職員は、お題を連想させる単語を5〜10個程度考え、それぞれの単語をカードに記入します。(例:(お題が「ポスト」の場合)郵便、赤い、手紙、投函など)カードはすべて裏返しにしておきます。
③ゲームを開始します。各チームは順番に1枚ずつヒントカードをめくります。めくったカードの言葉から、お題が何かをチーム内で話し合い、1回だけ回答できます。もし不正解だった場合は、次のチームが順番にカードをめくり、同様に推測を行います。
④より少ないヒントカードの枚数でお題を当てたチームが勝ちです。最後まで誰も当てられなかった場合は、最もお題に近い回答をしたチームに得点を与えるのもよいでしょう。
川柳作り
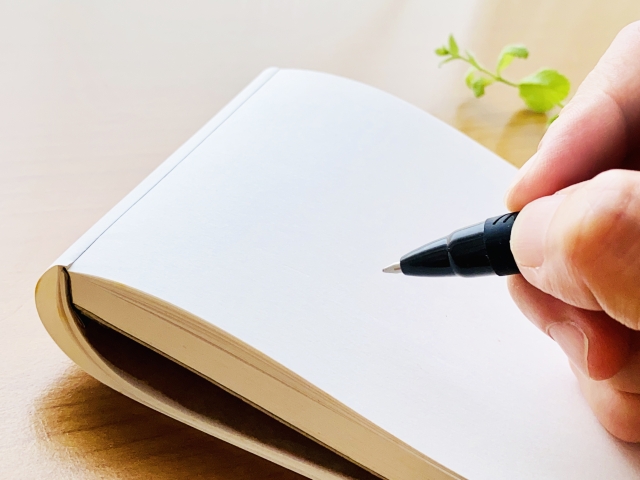
川柳は創造力を刺激し、脳の活性化につながる言葉遊びゲームです。季節に合わせて、「桜」「夏休み」「紅葉」「雪遊び」などのテーマを決めて、自由に川柳を作ってもらいましょう。最後に作品を発表し、参加者同士で感想を共有することで、皆でわいわい盛り上がることができます。
■準備するもの
- 配布用の「川柳用紙」やメモ紙
- 川柳のルールや例を説明するためのホワイトボード
■やり方
①川柳のテーマを決めます。参加しやすいように、身近なテーマを設定すると盛り上がりやすくなります。
- 季節:「春」「梅雨」「お正月」
- 施設生活:「今日の昼ごはん」「お風呂の時間」「職員さん」
- 思い出:「子どもの頃」「おじいちゃん・おばあちゃん」「昔の遊び」
②川柳のつくり方を簡単に説明します。川柳は五・七・五の17音。季語や難しい表現は不要。自由でOKです。
③ 「例」を2〜3つ見せてイメージをつかんでもらいます。
④「川柳用紙」やメモに書き込んで作成してもらいます。
⑤川柳が出来たら発表します。自分の作成した川柳を読み上げて発表してもらい、発表が終わったら拍手しましょう。
⑥壁や廊下に掲示して楽しんだり、感想を言い合っても良いでしょう。
伝言ゲーム

「伝言ゲーム」は、多くの人が参加でき、笑いが生まれやすい言葉遊びゲームです。正確に伝わると達成感があり、間違えても思わぬ珍回答が出て盛り上がること間違いなし。短期記憶を使うので、脳トレにも効果的です。
耳が遠い方がいる場合は、糸電話を活用したり、ジェスチャーや文字、イラストを取り入れたりすると、より多くの方が楽しめるでしょう。利用者さんの状況に合わせた工夫が大切です。
■準備するもの
- お題カード(あらかじめ用意しておくとスムーズ)
- ホワイトボード(正解発表用。なくてもOK)
■やり方
①3〜6人程度で1チームに分けます。椅子を一列に並べると進行がわかりやすいです。
②各チームの先頭の人に、こっそりお題を伝えます(職員が耳打ち、またはカードを見せる)お題は1文の短い文章がベストです。
例:
「今日のおやつはたい焼きです」
「さくらの花が満開です」
③最初の人は、後ろの人の耳元でこっそりお題を伝えます。最後の人まで順に伝えていき、最後の人がみんなの前で発表します。
④元のお題と比べてどう変わったか確認します。1人ずつ発表形式にして、どこでズレたかをみんなで当てるのも盛り上がります。
クロスワードパズル

クロスワードパズルはゲーム感覚で取り組めるため、楽しく続けやすい脳トレです。難易度を調整できるため、利用者のレベルに柔軟に合わせることが可能です。また、紙と鉛筆で書く動作は、手先の運動にもなるため、軽いリハビリ効果や、文字を読むことで視覚からの情報処理も活性化されます。季節のテーマや行事に合わせた内容にすることで、季節感のあるレクリエーションにもなります。
■準備するもの
- クロスワードの問題用紙(A4サイズ程度で、大きめのマス&文字がおすすめ・難易度を調整した複数パターンがあると◎)
- 筆記用具
- 回答見本
■やり方
①問題を配布します。一人1枚 or チームで1枚ずつ配布します。テーマは季節の言葉や食べ物、動物、ことわざなど身近で親しみやすいテーマがおすすめです。
②解答してもらいます。
③正解を全体で確認します。正解はホワイトボードに表示しても良いです。
あいうえお作文
高齢者向けの「あいうえお作文」は、言葉を使って創造的な表現を楽しむことができるレクリエーションです。認知機能の活性化や、言葉を使う楽しさを感じてもらえる活動です。
■準備するもの
- 「あいうえお作文」のルールを説明するための例文
- ペンやマーカー
■やり方
①まずはあいうえお作文のルールを説明します。「あ」→「ありがとう」、「い」→「いっしょに」、「う」→「嬉しい」など文字ごとに1つずつ文を作り、全部で5行をつなげて1つの作文を完成させます。
②参加者に作文を作ってもらいます。個人で考えてもグループで考えても良いです。
③完成した作文を、一人ずつ発表します。発表の際には、参加者同士で拍手をしたり、感想を言い合うと楽しい雰囲気が生まれます。
逆さ読みゲーム
「逆さ読みゲーム」は、言葉を逆さまに読んだ言葉を当てることで脳を活性化できる楽しいレクリエーションです。このゲームは、高齢者の認知機能の向上や反応力のトレーニングにも役立ちます。
■準備するもの
- 言葉リスト:逆さにして読んでも意味が通じる、または逆さにすると意味が変わるような言葉をリストアップします。
例
- るさ→さる
- ダンパ→パンダ
- ミズネリハ→ハリネズミ
■やり方
①ゲームのルールを説明します。進行役が逆さにした言葉を提示します。参加者はその逆さの言葉が何であるかを考え、答えることを目指します。ルールを理解しやすいよう、何個か例を出して練習してもらいましょう。
②職員が逆さまに行った言葉を出題して利用者に解答してもらいます。回答の際は手をあげたり、順番に答えてもらうようにします。
③ゲーム終了後、全員でどの言葉が難しかったか、面白かったかを振り返り、感想を共有します。これにより、コミュニケーションが活性化し、楽しい雰囲気が広がります。
指回し体操
座ったまま簡単にできる「指回し体操」も脳トレにおすすめです。指を動かすことで血行が促進され、手先の器用さや集中力の向上が期待できます。
<指回しの手順>
- 胸の前で両手の指先を軽く合わせる
- 親指から順に、左右交互に円を描くように回す
- 他の指が離れないよう意識しながら、すべての指で行う
薬指は特に動かしにくいため、「ゆっくりで大丈夫ですよ」と声かけをすると、利用者さんも安心して参加できます。
手話
「1日1手話」として、毎回1つずつ手話を覚えるのも脳トレになります。指や手の動きが脳を刺激し、認知機能の活性化につながります。
さらに、聴覚に不安のある利用者さんがいる場合は、コミュニケーションの幅を広げるきっかけにもなります。NHKの「手話CG単語検索サイト」で手話を知りたい単語を検索すると、手話の表現をCGアニメーションで確認できて便利なので、ぜひ活用してみてください。
まとめ
楽しみながら脳を活性化できる脳トレレクリエーションやゲームを16選ご紹介しました。今回ご紹介した脳トレはどれも簡単に取り入れやすく、認知機能や記憶力を刺激することができます。さらに、笑顔や会話が自然と生まれ、利用者様同士のコミュニケーションを促進し、盛り上がることができます。
毎日のレクリエーションに脳トレをぜひ気軽に取り入れてみてください。
