介護の基礎知識
【2024年改定対応】生産性向上推進体制加算の算定要件をわかりやすく解説
- 公開日:2025年03月28日
- 更新日:2025年06月16日

生産性向上推進体制加算は2024年の介護報酬改定で新設された加算です。算定要件や、どのようなテクノロジーの導入が必要かなど、詳細を理解して自事業所の加算に役立てたい事業所様も多いのではないでしょうか。本記事では区分や単位数、算定要件など、生産性向上推進体制加算について詳しく解説していきます。
生産性向上推進体制加算とは

2024年の介護報酬改定では、介護サービス事業所における生産性向上を評価するため、「生産性向上推進体制加算」が新たに設けられました。
この加算は、介護ロボットやICTなどのテクノロジーを導入することで、介護サービスの質を維持しながら、職員の負担軽減を図り、生産性向上の取り組みを推進することを目的としています。
生産年齢人口の減少と介護需要の増加という社会情勢の中で、介護人材の確保は大きな課題となっています。そのため、介護職員の処遇改善に加え、テクノロジーを活用した生産性向上の取り組みが重要な施策とされています。
生産性向上推進体制加算が新設された背景
介護業界では、介護を必要とする高齢者の割合が増える一方で、それを支える若い世代が減少する少子高齢化が人手不足の大きな原因となっています。
日本の65歳以上の人口割合は、2000年時点では17.4%でしたが、1971~1974年生まれの「団塊ジュニア世代」(いわゆる第二次ベビーブーム世代)が高齢者層に加わることで、2040年には34.8%に達すると見込まれています。少子高齢化の影響から、65歳以上の高齢者1人を支える現役世代の数は、2000年には3.9人でしたが、2040年にはわずか1.6人にまで減少します。2050年には、高齢者1人を支える現役世代の人数は、更に減り、1.4人にまで減少すると予想されます。
このような介護業界の人材不足の課題を解消する背景から生産性向上推進体制加算が新設されました。
生産性向上推進体制加算の対象となる介護サービス
生産性向上推進体制加算の対象となる介護サービスは以下の通りです。
- 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
- 介護老人保健施設
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 小規模多機能型居宅介護
- 介護付き有料老人ホーム
生産性向上推進体制加算の令和6年度介護報酬改定での変更ポイント
生産性向上推進体制加算は、令和6年度の介護報酬改定にて新設された加算です。この加算は、介護ロボットやICT機器などのテクノロジーを導入して、それを継続的に活用しながら介護サービスの質を保ちつつ職員の負担を軽減する取り組みを評価するものです。
具体的には、以下が求められます。
- 導入が必要なテクノロジー:1つ以上のテクノロジーを導入して活用すること。
- 提出が必要なデータ:一定期間ごとに、業務改善の効果を示すデータを提供すること。
- 生産性向上へ向けた委員会の設置:利用者の安全確保やケアの質の維持、職員の負担軽減などを検討する委員会の設置
- 業務改善の継続:生産性向上ガイドラインに基づき、業務改善を続けること。
これらを実施することで、テクノロジーの効果的な活用を支援し、介護現場の効率化やサービスの質の向上が期待されます。
生産性向上推進体制加算の単位数と算定要件
生産性向上推進体制加算には、加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)の2つの区分があります。加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)は段階的な仕組みとなっており、原則としてまずは加算(Ⅱ)を算定し、一定期間の取り組みを経て、加算(Ⅰ)へ移行することが想定されています。ただし、本加算の新設以前から生産性向上の取り組みを進めている事業所では、最初から加算(Ⅰ)を算定することも可能です。
それぞれの単位数と算定要件は以下の通りです。
生産性向上推進体制加算(Ⅱ):1ヶ月あたり10単位
算定要件は以下の通りです。
- 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていること。
- 見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入していること。
- 1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンラインによる提出)を行うこと。
生産性向上推進体制加算(Ⅰ):1ヶ月あたり100単位
算定要件は以下の通りです。
- (Ⅱ)の要件を満たし、(Ⅱ)のデータにより業務改善の取組による成果が確認されていること。
- 見守り機器等のテクノロジーを複数導入していること。
- 職員間の適切な役割分担(いわゆる介護助手の活用など)の取組等を行っていること。
- 1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンラインによる提出)を行うこと。
「職員間の適切な役割分担の取組」とは?
生産性向上推進体制加算(Ⅰ)では、「職員間の適切な役割分担の取り組み」が求められています。この取り組みは、業務内容の明確化や見直しを通じて職員間で役割を適切に分担し、業務の効率化とケアの質の向上を図ることを目的としています。
具体的な対応例として、以下のような取り組みが想定されています。
- 負荷が集中する時間帯の業務を細分化し、業務が特定の職員に集中しないよう平準化を図る。
- 特定の介護職員が利用者の介助に専念できる時間帯を設定する。
- 食事の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ごみ捨てなど、利用者の直接介助を伴わない業務を専門的に担う職員を設ける。
- 利用者の介助を伴わない業務の一部を外部委託する。
生産性向上推進体制加算算定に必要な4つのポイント
確実な加算取得に向けて押さえておく必要のあるポイントは、以下の4つです。
- 導入が必要なテクノロジー
- 提出が必要なデータ
- 生産性向上へ向けた委員会の設置
- 生産性向上ガイドラインの活用
それぞれ以下にて解説していきます。
①導入が必要なテクノロジー

生産性向上推進体制加算の算定には、以下のテクノロジーの導入が必要となります。
生産性向上推進体制加算(Ⅱ)取得に必要なテクノロジー
下記の3つのテクノロジーのうち、1つ以上を使用する必要があります。
1.見守り機器(利用者の離床状態等を感知し、職員に通知できる機器)
2.インカム(マイクロホンが取り付けられたイヤホンをいう。)やビジネス用のチャットツールの活用による職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器
3.介護記録ソフトウェア等の介護記録の作成の効率化に資するICT機器(複数の機器の連携も含め、データの入力から記録・保存・活用までを一体的に支援するものに限る。)
生産性向上推進体制加算(Ⅰ)取得に必要なテクノロジー
加算(Ⅰ)取得のためには、(Ⅱ)に記載されたテクノロジーのすべてを導入する必要があります。
特に、見守り機器はすべての居室に設置することが求められ、インカムなどのICT機器については、同一時間帯に勤務するすべての介護職員が使用できる体制を整える必要があります。介護現場へのテクノロジー導入を検討する際には、現場で抱える課題を明確にし、その課題を解決するために必要な種類のテクノロジーを慎重に選定することが重要です。また、テクノロジー導入の際は、利用者の安全確保と職員の負担軽減を両立する取り組みが求められます。
②提出が必要なデータ

生産性向上推進体制加算(Ⅱ)で提出が必要なデータと対象者
生産性向上推進体制加算(Ⅱ)の算定には、下記の1〜3のデータを提出する必要があります。
1.利用者の満足度等の評価
対象者:5名程度の利用者※
詳細:WHO-5調査 (利用者における満足度の変化) の実施、及び生活・認知機能尺度
2.総業務時間及び超過勤務時間の調査
対象者:介護機器の導入を行ったフロア等に勤務する介護職員
詳細:対象事業年度の10月における介護職員の1月当たりの 総業務時間及び超過勤務時間
3.年次有給休暇の取得状況の調査
対象者:介護機器の導入を行ったフロア等に勤務する介護職員
詳細:対象事業年度の10月を起点として直近1年間の年次有給休暇の取得日数
※介護機器の導入を行ったフロアや居室の利用者の数が5名に満たない場合は、当該利用者全員を調査対象とすることが必要です。
生産性向上推進体制加算(Ⅰ)で提出が必要なデータと対象者
生産性向上推進体制加算(Ⅰ)の算定には、下記の1~5のデータを提出する必要があります。
1.利用者の満足度等の評価
対象者:5名程度の利用者
詳細:WHO-5調査 (利用者における満足度の変化) の実施、及び生活・認知機能尺度
2.総業務時間及び超過勤務時間の調査
対象者:全ての介護職員
詳細:対象事業年度の10月における介護職員の1月当たりの 総業務時間及び超過勤務時間
3.年次有給休暇の取得状況の調査
対象者:全ての介護職員
詳細:対象事業年度の10月を起点として直近1年間の年次有給休暇の取得日数
4.介護職員の心理的負担等の評価
対象者:全ての介護職員
詳細:SRS-18調査 (介護職員の心理的負担の変化)及び 職員のモチベーションの変化に係る調査
5.機器の導入等による業務時間
対象者:複数人の介護職員
詳細:5日間の自記式又は他記式によるタイムスタディ調査
なお、加算(Ⅰ)の算定開始にあたっては、生産性向上の取り組みの成果として、以下の3点が確認される必要があります。
1.WHO-5調査等で利用者の悪化がみられないこと
2.介護職員の総業務時間及び超過勤務時間が短縮していること
3.年次有給休暇の取得日数が維持または増加していること
また、提出データの収集にあたっては、利用者と介護職員の負担軽減に配慮し、調査対象者の選定や同意取得を適切に行うことが求められています。
③生産性向上へ向けた委員会の設置

生産性向上推進体制加算を算定するには、利用者の安全確保やケアの質の維持、職員の負担軽減などを検討する委員会の設置が義務付けられています(ただし、3年間の経過措置あり)。
この委員会では、以下の4つの項目について検討を行い、3ヶ月に1回以上、取り組みの実施状況を確認し、必要に応じて改善を図ることが求められます。
- 利用者の安全確保およびケアの質の向上
- 職員の負担軽減および勤務環境への配慮
- 介護機器の定期点検
- 職員に対する研修の実施
委員会には、現場職員の意見を適切に反映させるため、管理者だけでなく、介護業務を行う職員やユニットリーダーなど、幅広い職種が参画することが必要です。
④生産性向上ガイドラインの活用

生産性向上推進体制加算を算定するには、「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン」(以下、生産性向上ガイドライン)に基づき、業務改善を実施する必要があります。
生産性向上ガイドラインは、生産性向上の具体的な取り組み方法を7つの視点から示したものです。
- 職場環境の整備
- 業務の明確化と役割分担
- 手順書の作成
- 記録・報告様式の工夫
- 情報共有の工夫
- OJT(職場内訓練)の仕組みづくり
- 理念・行動指針の徹底
このガイドラインは、介護現場での業務改善に直接活用できる内容となっており、事業所の課題に応じた取り組みを進めることで、生産性向上を図り、加算算定につなげることが期待されています。
ガイドラインの詳細は、厚生労働省の公式ウェブサイトをご参照ください。
生産性向上推進体制加算の解釈通知
生産性向上推進体制加算の解釈通知とは、厚生労働省が介護報酬改定や新設された加算の運用方法、具体的な解釈を事業所に周知するために発出する公式文書です。この通知は、加算の算定要件や実施基準の詳細、適用方法についての明確な指針を提供します。
本通知では、加算の算定要件や提出データの収集方法、様式例等が示されています。生産性向上推進体制加算の取得を検討する際は、これらの通知を確認し、適切な手順で取り組みを進めていくことが重要です。介護現場の生産性向上は、利用者の安全とケアの質を確保しつつ、職員の負担軽減を図るための重要な取り組みです。生産性向上推進体制加算を活用し、テクノロジーの導入と業務改善を計画的に進めることで、持続可能な介護サービスの提供につなげていきましょう。
テクノロジー導入に関する関連政策について
これまで、介護現場におけるテクノロジー導入を推進するため、以下のような施策が進められてきました。
- ICT機器や介護ロボット導入のための補助金・助成金制度
- 施設系サービスにおける夜間の人員配置基準の緩和
また、令和6年度の介護報酬改定では、特定施設における人員配置基準が条件付きで緩和されます。通常は、利用者3人に対して介護職員および看護職員を1人以上配置する必要がありますが、テクノロジーを導入して生産性向上に取り組んでいる施設では、0.9人の配置が認められます。
さらに、短期入所療養介護や介護老人保健施設においても、夜間帯の人員基準が見直されました。これまでは夜間帯に2人以上の職員を配置する必要がありましたが、見守り機器などのテクノロジーを導入した場合には、1.6人以上の配置で基準を満たすことが可能となります。
生産性向上推進体制加算に関するよくある質問(Q&A)
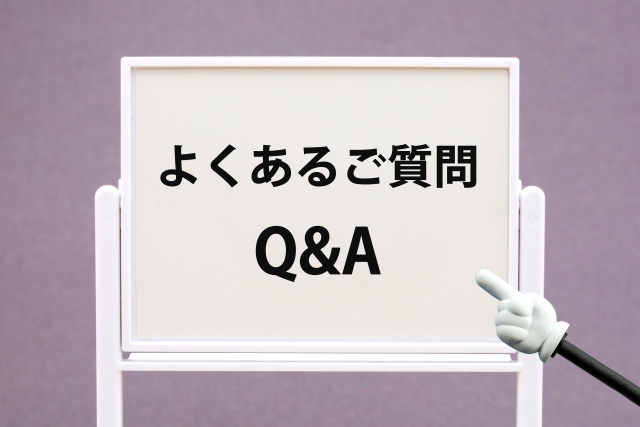
ここでは、「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)」で紹介されている、生産性向上推進体制加算のQ&Aをご紹介していきます。
Q.加算(Ⅱ)の要件となる介護機器の導入前後の比較が困難な場合はどのように考えるべき?
加算(Ⅰ)(※100 単位/月)の算定開始に当たっては、加算(Ⅱ)の要件となる介護機器の導入前後の状況を比較し、生産性向上の取組の成果の確認が求められているが、例えば、数年前又は新規に介護施設を開設し、開設当初より、加算(Ⅰ)の要件となる介護機器を全て導入しているような場合については、当該介護機器の導入前の状況を把握している利用者及び職員がいないなど、比較が困難となるが、導入前の状況の確認はどのように考えるべきか。
A.利用者へのヒアリング調査や介護職員の1ヶ月当たりの勤務状況を調査する
利用者の満足度等の評価について
介護サービスを利用する利用者(5名程度)に、介護機器を活用することに起因する利用者の安全やケアの質の確保についてヒアリング調査等を行い(※)、その結果に基づき、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会において当該介護機器の導入による利用者の満足度等への影響がないことを確認すること。
(※)介護機器活用した介護サービスを受ける中での、利用者が感じる不安や困りごと、介護サービスを利用する中での支障の有無、介護機器活用による効果等についてヒアリングを実施することを想定している。また、事前調査が実施できない場合であって、ヒアリング調査等を行う場合には、別添1の利用者向け調査票による事後調査の実施は不要となる。
総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間の調査、年次有給休暇の取得状況の調査について
加算(Ⅱ)の要件となる介護機器を導入した月(利用者の受入れを開始した月)を事前調査の実施時期(※)とし、介護職員の1月当たりの総業務時間、超過勤務時間及び年次有給休暇の取得状況を調査すること。また、事後調査は、介護機器の導入後、生産性向上の取組を3月以上継続した以降の月における介護職員の1月当たりの総業務時間、超過勤務時間及び年次有給休暇の取得状況を調査し、事前調査の勤務状況と比較すること。
(※) 介護施設を新たに開設し、利用者の受入開始月から複数月をかけて利用者の数を拡大するような場合については、利用者数の変化が一定程度落ち着いたと考えられる時点を事前調査の対象月とすること。この場合、利用者数の変化が一定程度落ち着いた考えられる時点とは、事前調査及び事後調査時点における利用者数と介護職員数の比に大きな差がないことをいう。
(例) 例えば、令和6年1月に介護施設(定員 50 名とする)を新たに開設し、同年1月に 15 人受け入れ、同年2月に 15 人受け入れ(合計 30 名)、同年3月に 15 人受け入れ(合計 45 名)、同年4月に2名受け入れ(合計 47 名)、のように、利用者の数を段階的に増加していく場合については、利用者の増加が落ち着いたと考えられる同年4月を事前調査の実施時期とすること。
まとめ
2024年の介護報酬改定で新設された「生産性向上推進体制加算」は、介護現場の業務効率化やICT活用を後押しする重要な加算です。算定には、体制の整備や職員への研修実施、ICTツールの活用状況など複数の要件を満たす必要があるため、早めの準備がポイントです。
制度の趣旨を理解し、自事業所の現場に合った取り組みを進めていくことで、利用者のサービス品質を保ちながら働きやすい職場づくりにもつながります。加算算定を通じて、日々の業務を見直し、働きやすい職場づくりにつなげましょう。
