介護の基礎知識
デイサービスの送迎表の記入項目とルート作成の効率化を行うポイントや作成における注意点
- 公開日:2025年07月30日
- 更新日:2025年07月30日

デイサービスにおける送迎業務は、利用者の安全を守り、サービス全体の信頼性を高めるうえで欠かせない重要な業務のひとつです。その送迎をスムーズかつ正確に行うためには、「送迎表」の活用が一般的です。
本記事では、送迎表の基本的な記入項目と作成時の注意点、効率的に送迎ルートを作成するための工夫やポイントについてわかりやすくご紹介します。
デイサービスの送迎表とは?

デイサービスの送迎表とは、利用者の送迎業務を円滑かつ安全に行うために作成される予定表のことです。主に、誰を・いつ・どこから・どこまで送迎するかといった情報が一覧で整理されています。
送迎表に記載される主な内容は以下の通りです。
- 利用者の氏名
- 送迎予定日・時間(迎え/送り)
- 住所・送迎場所(自宅、施設、集合場所など)
- 利用者ごとの注意点(乗降時の介助が必要、付き添いが必要など)
- 担当するドライバーや同行職員の氏名
- 車両の種類や台数、ルート情報
この送迎表は、送迎担当者だけでなく、職員全体で共有されることが多く、利用者の安全確保や業務の効率化に欠かせない資料です。また、送迎の直前に変更が発生することもあるため、リアルタイムで修正・確認しやすい形で運用することも重要なポイントとなります。
最近では、紙ではなく介護ソフトやアプリを活用して、送迎表をデジタル管理する事業所も増えており、ルートの自動作成や変更通知の簡略化など、さらなる効率化が図られています。
送迎表を使用する目的とは?

デイサービスにおいて送迎表を使用する目的は、送迎業務を安全かつ効率的に行うためです。利用者一人ひとりの住所や送迎時間、介助の有無などを正確に把握し、送迎ミスや事故を防ぐことが主な目的です。
具体的には、以下のような目的があります。
1. 利用者の安全確保
送迎表により、「誰を・いつ・どこから・どこへ」送迎するかが明確になります。これにより、利用者の乗り忘れや送り間違いを防止し、安全な送迎を実現します。
2. 業務の効率化
ルートやスケジュールが可視化されることで、無駄のない順路や最適な車両の割り当てが可能になります。複数の職員が関わる場合でも、情報を共有しやすくなります。
3. 職員間の情報共有
送迎に関する注意点(介助の有無、体調の留意点など)を記載することで、送迎担当者だけでなく全職員で利用者情報を共有できます。引継ぎミスや対応漏れを減らす効果があります。
4. ルートや時間のミス防止
利用者ごとの送迎時間や順番が明記されていることで、時間の勘違いやルート間違いといったヒューマンエラーを減らすことができます。地図付きの送迎表やナビ連携機能を活用する事業所も増えています。
5. 緊急時の対応に備える
万が一のトラブル時にも、送迎表があれば誰が・どのルートで・どの車両で対応しているかが即座に把握できるため、迅速な対応が可能になります。
送迎表は、ただの予定表ではなく、安全管理・効率運営・情報共有の要となる重要なツールです。紙でもデジタルでも、使いやすく整備された送迎表の活用が、デイサービス全体の質を高める第一歩となります。
送迎表に記載すべき主な項目とその書き方

送迎表は、誰が・いつ・どこから・どこへ送迎されるのかを明確に示す一覧表であり、ドライバーや添乗職員にとって重要な業務指示書です。ミスを防ぎ、スムーズかつ安全な送迎を行うためには、以下の情報を正確に記載することが求められます。
車両・車両ナンバー
使用する車両の名称やナンバーを記入します。同一車種の車両が複数ある場合や、事業所で独自に「1号車」「2号車」といった呼称を使用している場合は、車両名と番号を組み合わせて記載することで混同を防ぐことができます。
運転手・添乗者
それぞれの車両を担当する運転手と添乗者(介助スタッフ)の氏名を記載します。明確にしておくことで、トラブル発生時や対応の振り返りがしやすくなります。
送迎順・利用者名・住所・到着予定時間
送迎の順番に沿って、利用者の名前と住所を記入します。到着予定時間は、利用者宅への到着・出発を見積もって算出し、スタッフ全員が時間配分を把握できるようにします。特に、乗降りに時間を要する利用者には余裕をもたせましょう。
電話番号(利用者連絡先)
送迎時の遅延や不在といった事態に備えて、利用者またはご家族の連絡先を記載しておきます。
キャンセル
当日朝の体調不良などで送迎を中止するケースもあります。その場合は「キャンセル」欄にチェックを入れるなどして記録し、ルートの見直しや対応漏れを防ぎます。
備考欄・全体備考
送迎に関する特記事項を自由に記載する欄です。たとえば以下のような情報を記入します。
- 利用者の体調や注意点(乗降時に手助けが必要など)
- 利用の中止や変更の有無
- 送迎ルートでの注意点(渋滞箇所、工事情報など)
- 車両に関する気づきや職員間で共有すべき情報
備考欄は、送迎全体の安全と効率を高めるための情報共有の場として活用しましょう。
デイサービスの送迎ルートを作成する方法3選
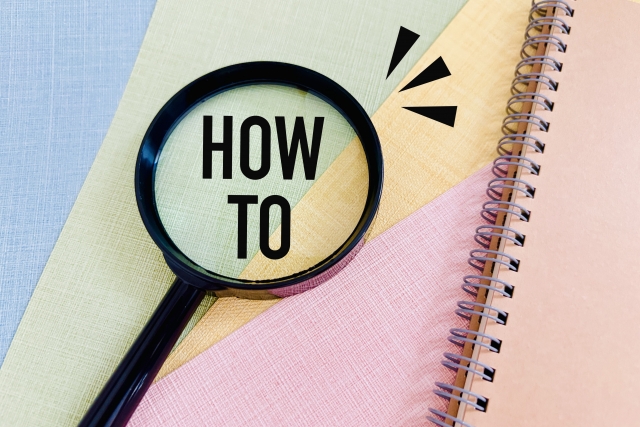
デイサービスのルート作成の方法は、送迎表の作成以外にも、地図を使ってルートを検討する方法やICTを活用して自動でルート作成する方法があります。ここでは、実際に現場で活用されている送迎ルートの作成方法をいくつかご紹介します。
① 送迎表を作成する
最も基本的な方法が、手書きやExcelなどで送迎表を作成する方法です。利用者ごとの住所、送迎時間、必要な介助内容などを整理し、それをもとに職員がルートを検討します。送迎順や時間を記入した送迎表は、運転担当者やヘルパーとの情報共有にも活用されます。
ポイント
- 小規模事業所や利用者数が少ない場合に適している
- 定期的な見直しと記録の保管が必要
- 利用者の増加や変更に対して柔軟に対応できる体制を整えることが重要
② 地図を使ってルートを検討する
紙の地図やGoogleマップなどの無料地図サービスを活用してルートを可視化する方法も効果的です。利用者宅を地図上にプロットすることで、地理的な位置関係が一目でわかり、移動順序の最適化に役立ちます。
ポイント
- 距離や順路を感覚的に把握しやすい
- 一方通行や渋滞エリアなど現地の事情も考慮することが必要
- 手作業なので、調整に時間がかかる可能性あり
③ ICTを活用して自動でルート作成
近年では、送迎ルートの自動作成機能を持った介護ソフトや送迎支援ツールが多数登場しています。利用者情報(住所・介助内容・曜日ごとの利用予定など)を入力することで、システムが最適なルートと車両の割り当てを自動で提案してくれます。
ICT活用のメリット
- 車いす対応などの条件も踏まえた配車が可能
- 渋滞や道路状況を考慮したリアルタイムルート作成
- 送迎表の自動生成・更新ができるため業務時間を大幅に削減
- GPS連携により送迎車の現在地確認や遅延連絡もスムーズ
デイサービスの送迎を効率化させるルート作成のポイント

デイサービスの運営において、送迎業務は職員の負担が大きく、時間や人手を大きく左右する重要な業務のひとつです。特に送迎ルートの組み方次第で、移動時間・待機時間・ガソリン代・人件費に大きな差が出るため、ルート作成の工夫が求められます。ここでは、送迎を効率化させるためのルート作成のポイントをご紹介します。
1. 地図と時間の両面から考える
単純な距離だけでなく、実際の走行時間や交通状況(朝夕の渋滞など)も考慮しましょう。特に都市部では「近いのに遅い」「一方通行で遠回りになる」などの落とし穴があります。
2. 利用者の住所を正確に把握・分類
送迎対象の利用者の住所を地図上で整理し、エリアごとにグループ分けをしてからルートを組むと、無駄な移動を減らせます。地図アプリや介護ソフトの地図機能を活用するとスムーズです。
3. 利用者の体調・介助状況を考慮する

送迎順は単に場所だけで決めるのではなく、長時間の乗車が負担となる方を優先して降ろす/乗せる工夫も必要です。車酔いしやすい方、体調が不安定な方、認知症が進行している方などは、配慮した順番にしましょう。
4. 定員と車両数を前提にルートを組む
送迎車の定員を超えないように配車することはもちろん、複数台ある場合は「どの車がどのルートを回るか」を事前に明確にしておきましょう。ドライバーの慣れたルートを活かすなどもポイントです。
5. 実績データをもとに見直しを
送迎ルートは一度作ったら終わりではなく、実際の所要時間や遅延状況などの実績をもとに、定期的に見直すことが重要です。月1回の見直しをルール化する事業所もあります。
6.事業所から遠い利用者からお迎えに行く
デイサービスの送迎では、事業所から遠い利用者から先にお迎えに行くのが一般的なルート設計の基本です。最初に遠い方をお迎えし、次々と近場の利用者を乗せながら事業所に向かうと、車内での待機時間を最小限にできます。
「乗車時間」「体調の配慮」「道路の混雑状況」についても考慮する必要があるため、必ずしも近い順とは限らない点に注意が必要です。
7.ご家族や利用者に、お迎えが遅れるケースがあることを伝えておく

送迎業務は、できるだけ定時に沿って行うことを基本としていますが、以下のような理由で予定より到着が遅れるケースも発生します。
- 交通渋滞や悪天候による遅延
- 先に訪問した利用者への介助に時間がかかった
- 体調不良等による急なキャンセルや順番の変更
- 道路工事・通行止めなどによるルート変更
こうした予期せぬ事態に備えて、あらかじめご家族や利用者に「多少の前後がある場合がある」ことを伝えておくことで、無用な不安や混乱を防ぐことができます。
デイサービスの送迎に関する注意点

デイサービスの送迎は原則利用者の自宅と事業所の間
デイサービスの送迎は、原則として「利用者の自宅」と「事業所(施設)」の間を対象としています。通常は、利用者の自宅玄関での乗降が基本ですが、転倒リスクが高い方や身体状況によっては、自室内まで介助を行う場合もあります。たとえば、ベッドからの起き上がりや車いすへの移乗など、安全を確保するために必要な支援が求められるケースです。
一方で、送迎先が自宅以外(例:駅・病院・親族宅など)であることは原則認められていません。ただし、利用者または家族のやむを得ない事情がある場合に限り、例外的に自宅以外への送迎が可能となることもあります。その際は、各自治体(市町村)による判断が必要であり、事前に相談・確認を行うことが重要です。
また、令和3年度の介護報酬改定では、通院時の乗降介助に関する制度(通院等乗降介助)の内容が見直されました。これにより、事業所と病院間の送迎なども条件付きで対応できるようになりましたが、自宅と事業所間の送迎を行わない場合は「送迎減算」が適用される点に注意が必要です。
送迎記録を残す必要がある
デイサービスにおいて送迎を実施した場合には、適正にサービスが提供されたことを示す証拠として「送迎記録」を残すことが推奨されます。これは、通所介護の提供時間の確認や、介護報酬請求の正当性を証明するためにも重要な役割を果たします。記録方法については推奨されている記録様式はありませんが、出発時間や到着時間などの項目は送迎の管理や運営に役立つため、記録しておくと良いでしょう。
通所介護事業所を対象とした運営指導(旧:実地指導)の際には、「送迎記録」が確認文書のひとつとしてチェックされます。記録がない送迎は“サービスを提供した証拠がない”と見なされてしまう可能性があるため、自治体によって異なる部分ではありますが、送迎時間についての記録は残しておいたほうが望ましいでしょう。
まとめ

送迎表は、日々の送迎業務を安全かつ正確に行うための基本のツールです。利用者の情報や送迎順、車両や職員の配置までを一元管理できる送迎表を正しく作成・活用することで、ヒューマンエラーの防止や業務効率の向上、職員間の情報共有の強化につながります。
また、送迎表をしっかりと整備することは、万が一の緊急時や担当者の変更時にも、スムーズな引き継ぎができる体制づくりにも貢献します。現場に合った様式や運用ルールを工夫することで、送迎の質と効率を高めましょう。
