介護の基礎知識
グループホームで訪問看護は使えるの?利用可能な入居者の条件や加算について解説
- 公開日:2025年07月01日
- 更新日:2025年10月23日

グループホームは、認知症のある方が家庭的な環境で生活を続けられるよう支援する介護施設です。認知症高齢者は、病状の変化や慢性疾患の合併などにより、医療的なケアが必要になることも少なくありません。
本記事では、グループホームにおける訪問看護について、利用可能な入居者の条件や加算、メリット・デメリットについて解説していきます。介護サービス事業所や居宅介護支援での利用者への案内や、グループホームでの対応などのご参考になれば幸いです。
グループホームで訪問看護を受けられる対象者とは?

原則として、グループホームで訪問看護は利用できません。なぜなら、グループホームは「身体的には元気な認知症の方」を対象としているからです。
ですが、グループホーム(認知症対応型共同生活介護)に入居している方でも、「主治医から特別訪問看護指示書を交付されている方」「厚生労働大臣が定める疾病がある方」は訪問看護を利用することができます。また、グループホームで訪問看護を利用する場合、介護保険ではなく、医療保険を使って利用することになります。グループホームで訪問看護が利用できる2つのケースについて、それぞれ以下にて説明します。
主治医から特別訪問看護指示書を交付されている方
主治医から「特別訪問看護指示書」を交付されている方は、グループホームに入居しながら訪問看護を利用することができます。
特別訪問看護指示書とは、病状が急変したり一時的に医療的管理が必要になった場合に、医師が緊急性を判断して発行する指示書です。通常の訪問看護では週3回までの訪問が上限ですが、この指示書により1日複数回や毎日の訪問も可能になります。
特別訪問看護指示書が発行される主なケースは以下の通りです。
- 病状が急変し、容体の観察や医療処置が一時的に必要となった
- 急な悪化で在宅看取り体制の強化が求められる
- 傷病により頻繁な看護的対応が必要になった
有効期間は、発行日から14日間限定です。再発行も可能ですが、医師の医学的判断に基づく必要があります。急性期の在宅ケア支援に用いられるため、緊急対応や看取り期などに活用されるケースが多いです。
厚生労働大臣が定める疾病がある方
厚生労働大臣が定める疾病がある方は、訪問看護療養費の特例扱いとなり、グループホームに入居しながら訪問看護を利用することができます。厚生労働大臣が定める疾病とは、以下の19種類の疾病と1つの状態を指します。
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患
- 多系統萎縮症
- プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライソゾーム病
- 副腎白質ジストロフィー
- 脊髄性筋萎縮症
- 球脊髄性筋萎縮症
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 後天性免疫不全症候群
- 頸髄損傷
- 人工呼吸器を使用している状態
これらの疾患に該当する場合は、医療保険での訪問看護が週3回以上可能になり、必要な看護が提供されます。
グループホームが訪問看護ステーションと契約している場合は「医療連携体制加算」が算定される

グループホームが訪問看護ステーションと契約している場合、入居者の方は介護保険を使って訪問看護を受けることが可能です。このときの訪問看護にかかる費用は、グループホームの月額利用料に「医療連携体制加算」として反映され、利用者がその一部を負担します。なお、訪問看護ステーションには、グループホーム側から委託費用として支払いが行われます。
医療連携体制加算の算定要件と単位数
医療連携体制加算(Ⅰ-イ)57単位/日
- 事業所の職員として看護師を常勤換算で1名以上配置していること。
- 事業所の職員である看護師、または病院、診療所、訪問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連絡できる体制を確保していること。
- 重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。
医療連携体制加算(Ⅰ-ロ)47単位/日
- 事業所の職員として看護職員を常勤換算で1名以上配置していること。
- 事業所の職員である看護師、または病院、診療所、訪問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連絡できる体制を確保していること。
- 重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。
医療連携体制加算(Ⅰ-ハ)37単位/日
- 事業所の職員として、または病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により、看護師を1名以上確保していること。
- 事業所の職員である看護師、または病院、診療所、訪問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連絡できる体制を確保していること。
- 重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。
医療連携体制加算(Ⅱ)5単位/日
- 医療連携体制加算(Ⅰ)のいずれかを算定していること。
- 直近3ヵ月において次のいずれかの状態の入居者が1名以上いること。
・喀痰吸引を実施している。
・経鼻胃管や胃ろうなどの経腸栄養がおこなわれている。
・呼吸障害により人工呼吸器を使用している。
・中心静脈注射を実施している。
・人工腎臓を実施している。
・重篤な心機能障害、呼吸障害などにより常時モニター測定を実施している。
・人工膀胱または人工肛門を実施している。
・褥瘡に対する治療を実施している。
・気管切開がおこなわれている。
・留置カテーテルを使用している。
・インスリン注射を実施している。
グループホームが訪問看護を行うメリット・デメリット
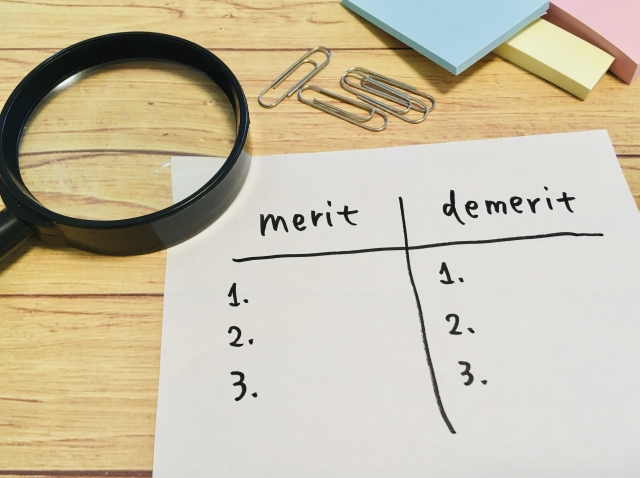
メリット:医療連携体制加算が算定できる
グループホームでは、医療ニーズのある入居者に対して、訪問看護ステーションと連携して必要な看護を外部から提供することができます。この際、一定の条件を満たすと「医療連携体制加算」が介護報酬として算定可能になります。
この加算があることで、施設側は訪問看護としっかり連携を取りつつ、より医療的な支援が必要な入居者を安定して受け入れられるようになります。また、看取り介護や慢性疾患管理など、グループホーム単体では対応しきれない医療ニーズに対しても対応しており、入居者にとっても安心感があります。
医療連携体制加算の算定要件
- 入居者が訪問看護を利用している
- 医師の指示書に基づき訪問看護計画が作成されている
- 医療ニーズの高い入居者に対して、緊急時の対応体制が整っている
- 看護師と介護職の情報共有・連携体制が確立されている
利用者にとってのメリット
- 医療処置(インスリン、褥瘡ケア、点滴など)が必要な状態でも、住み慣れたグループホームで暮らし続けられる
- 定期的な健康チェックや早期の体調変化の察知が可能になり、安心感がある
- 看取り期に向けた医師・看護師との連携がスムーズに進む
デメリット:訪問看護利用には契約料がかかる
グループホームで訪問看護を導入する際には、まず訪問看護ステーションとの業務委託契約を締結することが前提となります。
この契約にあたっては、グループホームが訪問看護ステーションへ契約料を支払う必要があり、その金額は一般的に、医療連携体制加算によって得られる収入の7〜10割程度を目安に設定されていることが多いようです。
また、訪問看護の利用開始にあたっては、訪問看護ステーションとの調整や契約手続きに加え、利用者やご家族への説明・同意取得などの事前準備も求められます。
そのため、職員の業務量が増加する可能性がある点にも注意が必要です。
主な負担内容
- 訪問看護サービスの自己負担分(介護保険または医療保険の1割〜3割)
- 緊急訪問や時間外対応に対する加算分
- 一部地域では契約手数料や導入時の初期対応費用が設定されることもあり
家族にとっての注意点
- グループホームの月額費用+訪問看護利用料の合計を見積もっておくこと
- 医療依存度が高くなると訪問回数が増え、費用も増加する可能性がある
- サービス導入にあたって「本人の同意書」「主治医の指示書」など手続きが必要になる
グループホームの訪問看護利用にあたっての現場の課題
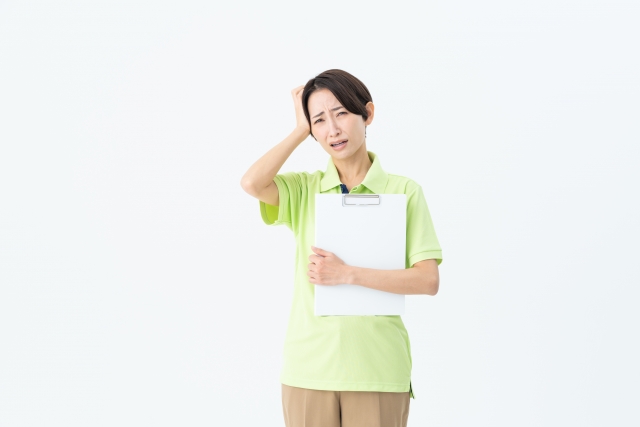
グループホームにおける訪問看護の利用にはメリットもある一方で、現場ではいくつかの課題や問題点も生じやすいのが実情です。特に、夜間対応、訪問看護の利用期間の制限、緊急時の情報提供体制といった点で、現場が戸惑うケースが少なくありません。
訪問看護による夜間の緊急対応がすぐに行えない場合がある
多くの訪問看護ステーションでは、日中の時間帯にサービスを提供しているところがほとんどで、夜間や早朝といった時間帯にはスタッフの配置や運用体制が整っていないケースが多く見受けられます。グループホームでは、入居者が深夜に体調を崩したり、急変することもあるため、本来であれば24時間体制の医療的支援が望ましい場合もあります。しかし、実際には「夜間の訪問は難しい」「緊急連絡しても来訪までに時間がかかる」といった課題があり、最終的には介護職員が一次対応を行うしかないという現場も少なくありません。
特別訪問看護指示書の期間では対応しきれない場合がある
特別訪問看護指示書は、医師が必要と判断した場合に発行され、14日間という期限付きで頻回の訪問看護が可能になる制度です。しかし、入居者の状態が悪い場合、14日間では対応しきれず、継続的な医療的ケアを必要とするケースもあります。指示書の延長には主治医の再評価と再発行が必要であり、現場では「延長のタイミングが難しい」「医師の判断を仰ぐのに時間がかかる」といった実務上の課題が発生します。結果として、介護スタッフが訪問看護の空白期間をカバーしなければならず、過重な負担を強いられることにもつながります。
救急搬送時の状況説明を介護職員が行う場合がある
グループホームでは看護職員が常駐していないことが多く、医療的な判断や緊急対応は主に訪問看護に委ねられています。しかし、夜間や不在時に急変が起きた場合、救急隊が到着した際の状態説明や病歴の確認などは、介護職員が行うことになります。医療的知識を持たない介護スタッフが、限られた情報と状況で適切に説明を行うのは容易ではなく、搬送先の医療機関との連携に支障をきたすリスクもあります。
グループホーム以外の認知症ケアと看護ケアを受けられる介護施設

グループホーム以外にも認知症ケアと看護ケアを同時に受けられる介護施設は以下の通りです。自施設の立ち位置の見直しや、利用者への案内、ケアマネの施設選定などにご利用ください。
介護付き有料老人ホーム
介護付き有料老人ホームは、介護保険上の「特定施設」の指定を受けているため、介護保険で訪問看護は利用できません。24 時間常駐の介護スタッフ+日中帯の看護職員が配置され、重度の認知症や中〜重度の要介護者でも比較的受け入れやすい介護施設です。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 医療・看護体制 | 看護師は日中常駐(※夜間オンコール)。提携医による定期往診。インスリン注射や胃ろうなど医療的ケアも相談可。 |
| 認知症ケア | 認知症ケア専門士を配置するホームが増加。回想法・音楽療法・個別リハビリなど多彩なプログラム。徘徊対策としてフロアごとの見守りシステムを導入する施設も。 |
| 費用感 | 入居一時金なしの月額制〜数千万円の前払金タイプまで幅広い。月額利用料は概ね 20〜35 万円台+介護保険自己負担。 |
| 入居条件 | 要介護1以上(要支援も可のホームあり)。認知症の診断があっても受け入れ可。 |
| メリット | 介護と生活支援を包括提供・看護師常駐で医療連携がスムーズ・レクリエーションが豊富 |
| デメリット | 費用が高め・医療依存度が極端に高いと退去要請の可能性 |
| 向いている人 | 「なるべくホテルライクな環境を保ちながら、将来的な重度化にも備えたい」方 |
住宅型有料老人ホーム
住宅型有料老人ホームの介護サービスは“外付け”方式となっており、訪問介護や訪問看護事業所と個別契約して必要な分だけ受ける仕組みのため、要支援~軽度要介護の方が主体のサービスです。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 医療・看護体制 | 看護師常駐は例外的。日中は介護職員のみのことが多く、医療的ケアは訪問看護に委託。 |
| 認知症ケア | スタッフ体制が少数のため、重度の周辺症状(BPSD)には対応しづらい。認知症対応型通所介護を併設するホームもある。 |
| 費用感 | 入居一時金 0〜数百万円。月額 12〜25 万円前後+外部サービス利用料。 |
| 入居条件 | 自立・要支援〜要介護3程度までを想定する施設が多い。 |
| メリット | 費用を抑えやすい・サービスを組み合わせてカスタマイズできる |
| デメリット | 24 時間看護体制は基本なし・認知症が進行すると住み替えが必要になることも |
| 向いている人 | 「今は比較的元気だが、いざという時に介護・看護を呼べる住まいを確保したい」方 |
サービス付き高齢者向け住宅
サービス付き高齢者向け住宅は高齢者住まい法に基づく「住宅」であり、バリアフリー構造と日中帯の生活相談員(常駐)が義務付け。介護・看護は外部サービスを利用する点で住宅型有料に似ています。国交省+厚労省の補助を受けた比較的新しい選択肢です。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 医療・看護体制 | 基本は外部訪問看護。看護師を配置している医療特化型サ高住も登場。 |
| 認知症ケア | 認知症専門フロアを持つサ高住もあるが、制度上は義務なし。要介護 3 以上は受け入れに制限がかかることも。 |
| 費用感 | 敷金 2〜3 か月+月額 10〜20 万円台。 |
| 入居条件 | 概ね60歳以上または要支援・要介護認定者。 |
| メリット | 賃貸契約なので“住まいの権利”が強い・見守りサービス付きで安心・初期費用が低い |
| デメリット | 介護・看護は外部依存のため重度化時に限界・スタッフが少なく夜間不安が残る |
| 向いている人 | 「元気なうちからシニア向けマンション感覚で転居し、いずれ訪問介護・看護を活用したい」方 |
特別養護老人ホーム(特養)
特別養護老人ホーム(特養)は公的施設として重度要介護者の最後の受け皿を担う施設です。看取り介護加算を取得する施設も多く、終の棲家として選ばれています。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 医療・看護体制 | 看護師は日中配置義務(夜間オンコール)。医療行為は限定的だが、協力医療機関との連携で看取りまで対応可能。 |
| 認知症ケア | 従来型多床室からユニット型個室まで形態は多様。ユニットケアは“暮らしの継続”を重視し、個別ケアを実践。 |
| 費用感 | 入居一時金なし。自己負担は年金内に収まるケースが多い(本人収入に応じた補足給付あり)。 |
| 入居条件 | 原則 要介護3以上。地域によっては待機者が数百〜数千人。 |
| メリット | 費用負担が小さい・重度認知症・終末期まで支援可能・多職種チームケア |
| デメリット | 入居待ちが長い・建物や居室の新旧差が大きい・レクリエーションや食事の選択肢は民間より少ない傾向 |
| 向いている人 | 「費用を抑えつつ、最期まで介護・看護を受けられる公的施設を希望」する方 |
認知症ケアや看護ケアを受けられる介護施設探しには紹介サービスを活用する方法もあります。例えば「静岡老人ホーム紹介タウンYAYA」は静岡県内で25年以上の老人ホーム運営実績があるアクタガワグループが運営しており、TVCMも放送しております。アクタガワグループの介護専門相談員が豊富な経験をもとに無料で老人ホーム探しからご入居まで、親身にサポートいたします。
まとめ:グループホームでの訪問看護の利用は条件を満たせば可能です

グループホームでも訪問看護は条件付きで利用でき、医療との連携体制を整えることで、より安心できるケア環境が実現できます。
ただし、利用には「主治医から特別訪問看護指示書を交付されている方」「厚生労働大臣が定める疾病がある方」に限られており、訪問看護ステーションとの契約や運用体制の構築など、事前に押さえておきたい実務上のポイントが多数あります。
ケアマネやサービス事業所にとって、訪問看護を正しく理解し、関係機関と協力してスムーズに導入・運用していくことは、入居者の生活の質を守る上でも欠かせません。
ぜひ本記事の内容を参考に、現場での対応や制度理解の一助としていただければ幸いです。
グループホームでの訪問看護の利用に備えて介護ソフトの導入がおすすめ

グループホームで訪問看護を導入・運用していくには、記録の正確な管理、職員同士のスムーズな情報共有、入居者の情報把握など、従来以上に複雑で高度な運営が求められます。特に、急変時の対応や医療連携加算の算定に必要な記録体制の整備は、現場にとって大きな負担となりかねません。
介護ソフトのトリケアトプスは、グループホームをはじめとする介護施設の現場ニーズに応えて開発された多機能型の業務支援ツールで、介護記録や入居者情報の管理を、ひとつのシステムで一元化することができます。
たとえば、入居者の基本情報・バイタル・ケア内容・医師の指示書などを一画面で把握でき、緊急時にも慌てることなく、正確でタイムリーな情報提供が可能になります。また、職員間の情報共有もスムーズになり、申し送りの漏れや二重入力の防止にもつながります。
介護の質を高め、安心・安全な医療連携を実現するには、正確な記録と強固な情報管理体制が不可欠です。
トリケアトプスは、そんな現場の負担を軽減しながら、ケアの質の向上と業務の効率化を同時にサポートしてくれる心強いパートナーです。
トリケアトプスが6,000以上の事業所様に選ばれてきたポイントは以下の4つです。
- 01 お得な料金体系
- トリケアトプスは従量課金制を採用しており、ご請求は使った分のみ。
最低220円/人~使用可能で、従量課金制の介護ソフトの中でも業界最安値です。上限価格もあるため、事業所の規模が大きくなって、思ったより負担が大きくなってしまった…なんてこともなく安心です。
オプションによる追加費用も無しで、全ての機能を標準装備で使用可能です。 - 02 パソコンが苦手な人でも使いやすい画面
- ケアマネジャーやヘルパーさん、どんな人でも使いやすいよう、直感的にどこに何があるか、分かりやすい操作画面を設計しました。
iOS/Androidのスマホアプリも対応しており、スマホからでも簡単に実績入力が行えます。
イメージキャラクターのトリケアちゃんが見守ってくれる、女性に人気の可愛い操作画面です♪ - 03 ご利用いただいている事業者様の92%が「サポートに満足」と回答
- 介護ソフトの使い方で分からないことがあれば、お電話頂ければ、専任のオペレーターが丁寧に対応致します。
開発元が運営も行っているため、わからないことは丁寧にしっかりとご説明することができます。
電話もつながりやすく、困っている時にすぐ頼っていただけます。 - 04 お客様のお声から機能を開発
- お客様から多くの声を寄せられた「こんな機能がほしい!」という機能を、他社では対応できないスピードでの実装を実現。ほぼ標準機能としてアップデートしているため、追加費用はいただきません。開発元がサポートも行っているため、ダイレクトに機能を反映することができます。
トリケアトプスは、最大3ヶ月間の無料体験を実施しています。 この機会にトリケアトプスをぜひお試しください。
