介護の基礎知識
介護の事故報告書の書き方やヒヤリハット報告書との区別|内出血の場合の記入例とは?
- 公開日:2025年05月27日
- 更新日:2025年08月22日
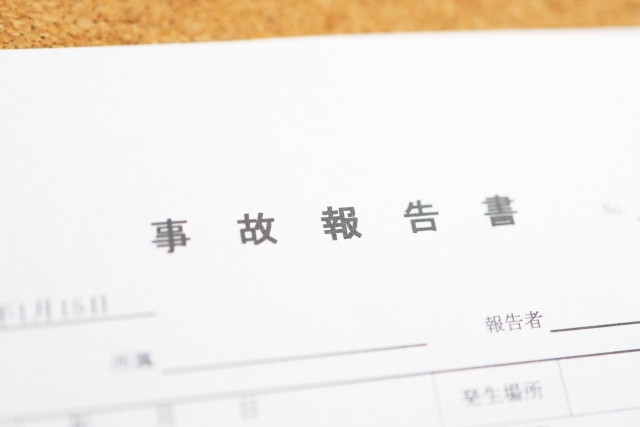
介護の現場では、どれだけ注意を払っていても予期せぬ事故が起こることがあります。転倒や誤嚥など、万が一の際に重要となるのが「事故報告書」です。特に、外傷や内出血などの身体的変化が見られる場合は、正確で簡潔な記録が求められます。この記事では、介護施設で事故報告書を作成する際の基本的なポイントと、「内出血を伴う転倒事故」の記入例をご紹介します。誰が読んでも理解しやすい報告書作成のコツを押さえ、再発防止やご家族への丁寧な情報共有に役立てましょう。
介護の事故報告書とは?
介護の現場で使われる事故報告書とは、介護施設や事業所で発生した事故について、事実関係を正確に記録・報告する文書です。事故の状況や、事業所や利用者の基本情報、事故の原因分析や再発防止案を記載し、自治体や利用者のご家族への報告の際に使用します。
「事故報告書」と「ヒヤリハット報告書」の違いは?

事故報告書の他に、「ヒヤリハット報告書」が存在します。事故報告書は転倒や転落などの事故が起こった際に記入するのに対して、ヒヤリハット報告書は事故には至らなかったものの、突発的な事象やミスで、ヒヤリとしたり、ハットしたりした事象を記入します。
「ハインリッヒの法則」では「1件の重大事故の背景には、29件の軽微なケガを伴う災害があり、その背景に300件の無傷の災害がある」という統計結果があります。重大な事故を起こさないためにもヒヤリハットの時点で報告を行い、事故の予防に繋げることが重要です。
ヒヤリハットと事故の区別とは?
ヒヤリハットは、重大事故に直結してもおかしくない一歩手前での発見を言います。例えば、「ブレーキが緩んでいたので、移乗介助中に車いすが動いてしまった」「ネジが取れストレッチャーの安全バーが突然外れた」「配薬に間違いがあり、違う薬を飲ませてしまいそうになった」などです。
しかし、実際には「転倒してケガをすれば事故報告」「転倒したけれどケガをしなかったのでヒヤリハット報告」としている事業所が多く見受けられます。これでは、事故とヒヤリハットが運に左右されることになり、事故が起こった場合も「運が悪かった」と解釈してしまい、根本解決には至りません。
「内出血があったが、出血していないためヒヤリハット報告で良いのか?」「内出血が小さかったのでヒヤリハット報告か?」など、傷の大小で判断するのではなく、基本的には内出血は事故扱いとなります。
なお、内出血の際にヒヤリハット報告のみ行っており、家族への連絡も行っていなかったため、家族が虐待を疑い、通報に至ったケースもあるため、判断は慎重に行いましょう。
事故報告書の目的
事故報告書の目的は以下の通りです。
再発防止のための検証材料とするため
事故報告書の最大の目的は、同様の事故が再び起こらないようにすることです。事故が発生した際、その状況や背景、要因を詳細に記録・分析することで、職場全体で原因を共有し、再発を防ぐための具体的な対策を講じることができます。たとえば、転倒事故であれば、床の状態や靴の滑りやすさ、職員の声かけの有無など、さまざまな角度から要因を検討します。このような記録が蓄積されることで、施設全体のリスクマネジメント体制が強化され、ご利用者様の安全がより確保される環境づくりへとつながります。
ご利用者・ご家族への説明責任のため
事故が起きた場合、ご家族に対して事実関係を正確かつ誠意をもって説明する責任があります。その際、事故報告書に記録された内容が大切な根拠となります。「いつ、どこで、誰が、どのような状況で事故に至ったのか」「その後どのような対応を取ったのか」など、時系列での説明が求められます。報告書が整っていれば、職員による口頭説明だけでなく文書でも情報提供でき、信頼関係を保つ助けとなります。また、説明を通じて、施設として事故を重く受け止めている姿勢を示すことができ、ご家族に対して安心感を与える役割も果たします。
関係機関(行政・保険者・監査機関など)への報告のため
重大な事故が発生した場合、介護保険法や各自治体の条例等に基づき、速やかに行政や保険者への報告が義務づけられているケースがあります。たとえば、骨折や誤嚥、救急搬送を要する事故、投薬・処置などの治療が必要な事故や死亡事故が該当します。こうした場合、報告書をもとに事実関係を明確に整理し、指定様式に沿って報告書を作成する必要があります。報告内容に不備があると、行政指導や監査対応において信頼を損ねる恐れがあります。そのため、事故報告書は単なる内部文書にとどまらず、対外的にも正確で客観性のある記録として活用され、法令遵守の証明として重要な役割を果たします。
職員教育や業務改善に活かすため
事故報告書は、現場の職員にとっても貴重な学びの材料となります。どのような場面で事故が起きやすいのか、予兆はあったのか、未然に防ぐことができたかなどをチームで振り返ることで、個々の気づきやチームワークの向上に繋がります。また、複数の報告書から共通の傾向が見えてくる場合もあり、その場合は施設全体の業務プロセスやマニュアルを見直すきっかけになります。特に新人職員にとっては、実際にあったケースを通してリスクへの感度を高める絶好の教材となり、安全意識の醸成にも効果的です。
法的トラブルの備えとして記録を残すため
介護現場では、事故の内容やその後の対応について、ご利用者やご家族と認識に差が生じることがあります。こうした行き違いがきっかけとなり、法的なトラブルに発展することもあります。その際、当時の状況や職員の対応を客観的かつ正確に記録した事故報告書は、非常に重要な証拠資料となります。いつ、どこで、誰が、何をしていたのか、どのように対応したのかを時系列で明記することで、施設側の説明に信頼性が生まれ、無用な誤解や不信感を防ぐことにもつながります。また、施設が事故を軽視せず、適切な手順で対応していることを示す姿勢としても評価されます。事故報告書は「記録に残す」という意識のもと、感情的な表現を避け、事実ベースで冷静に記述することが大切です。日頃からの丁寧な記録が、将来のリスク回避に直結します。
介護の事故報告書の記載項目
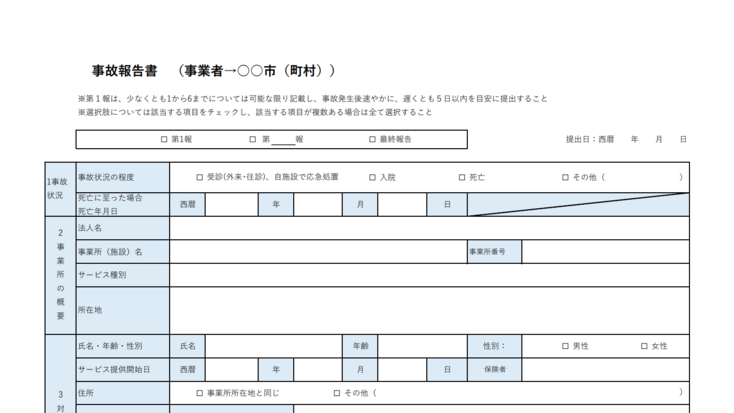
介護の事故報告書は、第一報と第二報があります。第一報では項目1〜6までを記載し、事故発生から5日以内に自治体へ提出する必要があります。第二報では、項目7〜9にて原因分析、再発防止案を記載し、利用者家族や自治体に提出します。
国が定めた様式に記載されている項目は、以下の9つです。
- 事故の状況
- 事業所の概要
- 対象者の概要
- 事故の概要
- 事故発生時の対応
- 事故発生後の状況
- 事故の原因分析
- 再発防止案
- その他
厚生労働省から提供されている事故報告書のExcel様式は以下よりダウンロードいただけます。
1. 事故の状況
まずは事故の状況を記載します。事故の程度は受診・入院・死亡のどの程度にあたるのかなどを記載します。死亡に至った場合は死亡した年月日を記載します。
2.事業所の概要
事故が発生した施設やサービスの基本情報を記載します。記載する項目は以下の通りです。
- 法人名
- 事業所(施設)名
- 事業所番号
- サービス種別
- 所在地
3.対象者の概要
事故の対象者(利用者)の基本情報を簡潔に記載します。記載する項目は以下の通りです。
- 氏名
- 年齢
- 性別
- サービス提供開始日
- 住所
- 身体状況
- 要介護度
- 認知症高齢者日常生活自立度
身体状況や要介護度を記載し、事故との関連を読み取れるようにします。認知症高齢者の場合は、日常生活の自立度も記載する必要があります。
4.事故の概要
事故が「どのように起こったのか」を具体的に記録します。記載する項目は以下の通りです。
- 発生日時
- 発生場所
- 事故の種別
- 発生時状況、事故内容の詳細
- その他特記すべき事項
できる限り客観的に、時系列に沿って記述します。感情的・憶測的な表現は避け、事実に基づいて書くことが重要です。
5.事故発生時の対応
事故発生直後の対応を記録します。記載する項目は以下の通りです。
- 発生時の対応
- 受診方法
- 受診先の医療機関名
- 医療機関の連絡先(電話番号)
- 診断名
- 診断内容
- 検査、処置等の概要
事故発生時の初期対応や医療機関での診断を記載します。
6.事故発生後の状況
事故発生後の影響や経過について記載します。記載する項目は以下の通りです。
- 利用者の状況
- 報告した家族等の続柄
- 家族等への報告年月日
- 連絡した関係機関(連絡した場合のみ)
- 本人、家族、関係先等への追加対応予定
なお事故が起きた5日以内に、項目1〜6までを報告する必要があります。「事故発生後の状況」まで記載し、自治体に報告します。
7.事故の原因分析
ここからの項目は、関係者による事故検証を行ったうえで記載します。特に項目7「事故の原因分析」では、事故の背景や要因について本人要因・職員要因・環境要因から多角的に検討し、協議の結果をもとに、事故に至った原因を客観的かつ具体的に記述してください。単なる推測ではなく、実際の状況や事実に基づいた分析を行うことが重要です。
8.再発防止案
事故の再発を防ぐために、具体的にどのような対策を講じるかを記載します。手順変更・環境変更・その他の対応・再発防止策の評価時期および結果等の観点からできるだけ具体的に記載するようにします。
9.その他
上記項目に含まれない、補足情報や連絡事項、注意点などがあれば記載して報告します。
令和3年度介護報酬改定により、事故報告書の様式が統一化されました

今まで、市町村によって事故報告書の様式が異なっていました。将来的に全国で事故情報を共有・活用するため、令和3年度の介護報酬改定にて事故報告書の様式が統一化されました。様式の統一化にあたり、以下の内容についても統一化が行われました。
- 報告対象
- 報告内容(様式)
- 報告期限
- 対象サービス
報告対象
国によって様式が統一化される前は、各自治体の作成基準に基づいて事故報告書を書くべきかを判断していました。変更後は以下のような事故については、原則として各自治体にすべて報告する必要があると定められました。
- 利用者が死亡した事故
- 医師(勤務医や嘱託医も含む)による診断のうえ、投薬・処置などの治療が必要になった事故
また、それ以外の事故についての報告は、各市町村の判断に従うこととされています。施設の所在地によって対応が異なるため、事前に自治体の方針を確認しておくことが大切です。
報告内容(様式)
今までは各自治体によって様式が異なりましたが、事故の報告を市町村へ提出する場合は、可能な限り、国が公表している「別紙様式」を使用するように定められました。報告の提出方法としては、電子メールによる提出が望ましいとされています。
これまで市町村で使われてきた独自の様式を使うことや、別紙様式を一部変更して使うことも可能です。ただし、その場合でも、国が示した別紙様式の項目をすべて含めるようにしてください。これは、将来的に事故報告の様式を全国で統一し、情報の蓄積や有効な活用につなげるための取り組みの一環です。
統一化された様式は以下よりExcelにてダウンロードいただけます。
報告期限
事故が発生した場合は、できるだけ速やかに、遅くとも5日以内を目安として、第1報を提出してください。このときは、別紙様式の1~6項目までをできるだけ詳しく記載します。
その後、ご利用者の状態や事故の状況に変化があった場合には、必要に応じて追加報告を行ってください。また、事故の原因分析や再発防止策についても、準備が整い次第、あわせて報告する必要があります。
対象サービス
この別紙様式は、もともと介護保険施設での事故報告用として作成されたものですが、以下のような施設・事業所でも、積極的に活用することが求められています。
- 認知症対応型共同生活介護(グループホームを含む)
- 特定施設入居者生活介護(地域密着型や介護予防を含む)
- 有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
また、それ以外の居宅系サービスで事故が起きた場合にも、可能な限り統一された様式を使用することが望ましいとされています。
介護の事故報告書の書き方のポイント

介護の事故報告書を作成する際は、事実に基づいた正確な記録と、再発防止につながる具体的な内容が求められます。以下のポイントを意識すると、信頼性が高く、現場で活用しやすい報告書になります。
事故の状況は事実に基づき、時系列で記載する
事故が起きたときの状況は、必ず時系列に沿って事実のみを簡潔に記録します。「〇月〇日〇時ごろ、〇〇で〇〇をしていたところ、〇〇が発生」といった形で、日時、場所、行動、状況を具体的に記します。主観やあいまいな表現は避け、第三者が読んでも理解できる内容にすることが大切です
職員の対応を正確に記録する
事故発生直後に行った対応についても、誰が・いつ・何をしたかを明確に記載します。応急処置や救急対応、医師・看護師への報告、ご家族への連絡など、対応の流れを丁寧に書くことで、事故後の適切な処置がとられたかを検証する材料になります。
ご利用者の様子や変化を丁寧に記録する
事故時やその後のご利用者の状態についても詳しく書く必要があります。身体の状態(出血や打撲の有無)、表情、痛みの訴え、混乱の有無など、目に見える反応や様子を具体的に記録しましょう。これにより、医療対応や今後のケアに役立つ情報となります。
原因を多角的に分析する
事故の原因は、環境(床の状態、照明、備品の配置など)、人的(職員の声かけ、見守り体制)、利用者本人の状態(認知症、筋力低下など)といったさまざまな要因から分析することが必要です。関係職員と共有・協議のうえ、客観的かつ多面的に検討しましょう。
再発防止策は具体的かつ実行可能に
原因分析の結果を踏まえた再発防止策は、具体性を持たせて記載します。たとえば、「注意する」ではなく「歩行時は必ず1名以上で付き添う」「床に滑り止めマットを設置する」など、実際に現場で実行できる内容にすることがポイントです。
報告は速やかに行う
報告書は、事故発生後できる限り早く、遅くとも5日以内に「第1報」として提出します。この段階では、基本情報や初期対応の内容までを記載し、後日、利用者の容体や分析結果、再発防止策が整い次第、「追加報告」を行います。タイミングを逃さず、状況に応じた報告を行うことが求められます。
専門用語や独自の略語は使わない
事故報告書を作成する際は、専門用語やその施設独自の略語は使わないようにしましょう。
この書類は、職員だけでなく、ご利用者やご家族、市町村、関係機関などさまざまな立場の人が目にする可能性があります。そのため、介護や福祉の専門的な知識がない方でも、内容を正しく理解できるように書くことが大切です。
事故報告書の記入例(転倒による内出血が起きたケース)

事故の状況
医療機関を受診
事業所の概要
法人名: 社会福祉法人岡谷システム
事業所(施設)名: デイサービス トリケアの郷
事業所番号: 13101000xx
サービス種別: 通所介護
所在地: 東京都〇〇市〇〇町x-x-xx
対象者の概要
氏名: 山田ケア子
年齢: 87歳
性別: 女性
サービス提供開始日: 2022年6月1日
住所: 東京都〇〇市〇〇町x-x-xx
身体状況: 四点杖使用による自立歩行可能。骨粗しょう症あり。
要介護度: 要介護3
認知症高齢者日常生活自立度: Ⅱb
事故の概要
発生日時: 2025年5月3日(木)13時10分頃
発生場所: 利用者の居室内
事故の種別: 転倒・打撲による内出血
発生時状況、事故内容の詳細:
昼食後にベッドから立ち上がろうとした際、足元がもつれ転倒。右膝をベッド角に打ちつけた。転倒直後は痛みの訴え少なく歩行に支障なし。その後、着替え介助時に右膝外側に10cm以上の内出血を確認。
その他特記すべき事項:
同様の転倒歴あり。日によってふらつきに波がある。
事故発生時の対応
発生時の対応: 看護師が患部を冷却し、痛みと腫れの程度を観察。内出血の広がりから嘱託医へ報告。翌日施設内診察を調整。
受診方法: 翌日施設内での嘱託医診察
受診先の医療機関名: 岡谷クリニック
医療機関の連絡先(電話番号): 03-1234-5678
診断名: 膝部打撲による皮下出血
診断内容: 骨折所見はなく、湿布処置と安静指示。経過観察。
検査、処置等の概要: 視診と触診による診察。湿布処方。冷却処置継続。
事故発生後の状況
利用者の状況: 痛みは軽度。歩行可能だが看護記録に留意し様子見中。腫れと変色に拡大傾向はなし。
報告した家族等の続柄: 長女
家族等への報告年月日: 2025年5月3日(木)17時40分
連絡した関係機関(連絡した場合のみ): なし
本人、家族、関係先等への追加対応予定: 経過観察のうえ、症状が変化した際は再度診察と報告対応を実施。
事故の原因分析
立ち上がり動作におけるバランス能力の低下と、床に設置していたマットが若干ずれていたことが転倒を誘発した可能性あり。本人の注意力低下や日内変動も影響したと考えられる。
再発防止案
・居室マットのズレ防止策として滑り止めを追加
・立ち上がり動作の際に職員の声かけや見守りを強化
・日中の身体状況に応じた歩行訓練や運動量の調整を検討
・転倒リスクの高い時間帯の記録を蓄積し対応に反映
その他
事故カンファレンスは5月6日に開催予定。全職員へ事例共有済み。必要に応じて環境整備と身体状況の見直しを進めていく。
まとめ:事故報告書は書き方を正しく理解し、再発防止に活かしましょう
事故報告書は、事故の記録だけでなく、再発防止やご家族への信頼構築にもつながる大切な文書です。専門用語を避け、事実を正確に、誰にでもわかりやすく記録することが大切です。
介護の仕事は、人の命や生活を支える責任ある現場です。どれだけ気をつけていても、事故はゼロにはできません。しかし、事故報告書を正しく記録し、振り返りや改善に活かすことで、より安全な環境づくりにつながります。職員一人ひとりの報告が、チーム全体の気づきと成長につながることを意識し、前向きに取り組んでいきましょう。
