介護の基礎知識
【2024年度改定対応】認知症専門ケア加算とは?算定要件や単位数、研修について
- 公開日:2025年02月13日
- 更新日:2025年06月16日

日本の高齢社会において、2025年には65歳以上の高齢者の約20%以上が認知症を発症すると予測されています。認知症の高齢者が年々増加していることから、より質の高いケアの提供が求められています。そのため、介護現場では「認知症ケア加算」が導入され、認知症の方々に適切なサービスを提供することの重要性が強調されています。
本記事では、認知症ケア加算の概要や算定要件、必要な研修について詳しく解説します。
認知症専門ケア加算とは?
認知症専門ケア加算とは、認知症に関する専門的な研修を修了した職員が介護サービスを提供した際に算定できる加算です。2021年度の介護報酬改定により、認知症対応力の向上を目的として、加算の対象となる事業所が拡大されました。
認知症専門ケア加算を取得できる対象事業者
認知症専門ケア加算を取得できる対象事業者は以下の通りです。
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 特定施設入居者生活介護
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
2024年の介護報酬改定による変更点
訪問系サービスにおける認知症専門ケア加算について、認知症高齢者の重症化の緩和や日常生活自立度Ⅱの者に対して適切に認知症の専門的ケアを行うことを評価する観点から、利用者の受入れに関する要件が見直されました。今回の報酬改定による単位数の変更はなく、算定要件のみ変更されました。具体的な変更箇所は以下の通りです。
認知症専門ケア加算の算定要件・単位数
認知症専門ケア加算の算定要件・単位数は以下の通りです。2024年の介護報酬改定における変更点は太字で記載しております。
認知症専門ケア加算(Ⅰ):3単位/日
認知症専門ケア加算(Ⅰ)の算定要件は以下の通りです。
- 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者が利用者の2分の1以上
- 認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者が20人未満の場合は1以上、20人以上の場合は1に、当該対象者の数が19を超えて10又は端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置
- 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合
- 当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催
認知症専門ケア加算(Ⅱ):4単位/日
認知症専門ケア加算(Ⅱ)の算定要件は以下の通りです。
- 認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者が20人未満の場合は1以上、20人以上の場合は1に、当該対象者の数が19を超えて10又は端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置
- 当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催
- 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の100分の20以上
- 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合
- 認知症介護指導者養成研修修了者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施
- 介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、研修を実施又は実施を予定
※ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護(Ⅱ)については、認知症専門ケア加算(Ⅰ)90単位/月、認知症専門ケア加算(Ⅱ)120単位/月
認知症専門ケア加算に必要な研修とは?

認知症介護実践リーダー研修
この研修は、認知症の方が持つ能力に応じて自立した生活を送れるよう支援することを目的としており、実践的な知識や技術を習得できます。
研修を受講することで、認知症の利用者やそのご家族に対して、より質の高いケアを提供できるようになり、認知症支援のチームリーダーとして職員の指導やチームケアの調整を行う役割を担うことができます。講義や演習に加え、他施設実習や自施設実習を通じて実践力を養います。
この研修は各都道府県や政令指定都市が実施しており、受験資格やカリキュラム、受講費用は自治体ごとに異なります。受講を希望する場合は、勤務先のある自治体のホームページで詳細を確認しましょう。
認知症介護指導者養成研修
認知症介護指導者養成研修は、認知症介護に関する専門的な知識や技術に加え、研修プログラムの作成方法や教育技術、介護の質を向上させるための指導方法などを習得する研修です。研修期間は9週間にわたり、300時間以上の実習や研修が行われます。
受講対象者は以下の条件を満たす方となっています。
- 医療・福祉に関する国家資格を有する者(またはそれに準ずる者)
- 認知症介護実践研修および認知症介護実践リーダー研修を修了した者(または同等の能力を有する者)
- 認知症介護実践研修の企画・立案、講師、地域ケアの推進を行う見込みのある者
この研修は厚生労働省が定める全国3か所の研修施設で実施され、受講場所は担当地域ごとに決められています。申し込みには推薦書や実践事例報告などの書類が必要となるため、事前に必要書類を確認し、準備を進めましょう。
認知症看護に関する研修
認知症看護に関する研修には、以下の3つがあります。
1. 日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」
認知症の方に質の高い看護を提供するため、専門的な知識と熟練した技術を習得する研修です。2020年度からは新たなカリキュラムが加わり、認知症看護認定看護師の活躍の場がさらに広がっています。
2. 日本看護協会が認定する看護系大学院の「老人看護」および「精神看護」専門看護師教育課程
この教育課程では、高齢者やその家族、グループに対して適切な看護を提供できるよう、老人看護や精神看護の実践力を養います。課程修了後、認定試験に合格することで、施設全体や地域の看護の質向上に貢献できる専門看護師として認められます。
3. 日本精神科看護協会認定「精神科認定看護師」
精神科領域における高度な看護技術や専門知識、指導方法を習得するための研修です。精神科認定看護師教育課程を修了し、認定試験に合格すると、認定証が発行されます。
認知症専門ケア加算取得のメリット
スタッフのスキル向上につながる
認知症専門ケア加算を算定するために必要な研修を受講することで、職員の認知症ケアのスキルが向上します。さらに、研修を受けた職員が他の職員にも知識や技術を共有することで、施設全体のスキルアップにつながります。
認知症専門ケア加算(Ⅰ)では、「認知症ケアに関する留意事項の伝達または技術的指導に関する会議」の定期開催が要件となっており、認知症専門ケア加算(Ⅱ)では「認知症ケアに関する研修計画」の作成が必要です。事業所全体で専門的な知識や技術を高め、職員一人ひとりのスキルアップを図ることが重要です。
利用者の受け入れがスムーズになる
認知症専門ケア加算を取得することで、適切で質の高いケアを提供できる事業所として評価され、認知症の高齢者が利用しやすい環境が整います。
また、ケアマネージャーが認知症専門ケア加算を算定している事業所を訪問介護先として優先的に紹介する可能性もあります。さらに、地域の施設や住民に対しても、専門性の高い認知症ケアを提供できる事業所として認知され、信頼を得ることにつながるでしょう。
事業所の収益向上が期待できる
認知症専門ケア加算を算定することで、事業所の収益増加も見込めます。訪問介護の場合、認知症ケア加算(Ⅰ)では1日3単位、認知症ケア加算(Ⅱ)では1日4単位を取得することが可能です。
事業所の収益が向上することで、さらなるサービスの充実や職員の待遇改善などにもつながり、結果的により良いケアの提供が実現できます。
認知症専門ケア加算の算定までの流れ

①算定要件を満たす人員配置や利用者割合を整える
認知症専門ケア加算を算定するには、認知症利用者の人数や対応する職員の研修修了状況など、細かな要件を満たす必要があります。事前に算定要件をしっかり確認しましょう。
例えば、認知症専門ケア加算(Ⅰ)を算定する場合、利用者が50人いる事業所では、日常生活自立度Ⅱ以上の認知症高齢者が25人以上いることが条件です。また、認知症介護指導者養成研修を修了した職員を2人以上配置する必要があります。
②算定に必要な書類を準備する
加算の算定を開始する際、または要件に変更がある場合や算定を終了する場合には、自治体への届出書の提出が必要です。
届出書には、認知症ケア加算(Ⅰ)または(Ⅱ)のどちらを算定するのか、利用者数や研修修了者の情報など、算定要件を満たしていることを記載します。自治体によっては、要件を証明する追加書類の提出を求められることもあるため、事前に確認しておきましょう。
③事業所が所在する自治体へ届け出る
書類が準備できたら、事業所の所在地を管轄する自治体に届け出を提出します。算定を開始する月の前月15日までに提出する必要があるため、スケジュールを確認しておきましょう。
また、算定要件を満たさなくなった場合には、速やかに自治体へ届け出を行う必要があります。自治体によっては事前予約が必要な場合もあるため、提出方法を事前に確認しておくとスムーズです。
認知症専門ケア加算についてのよくある質問
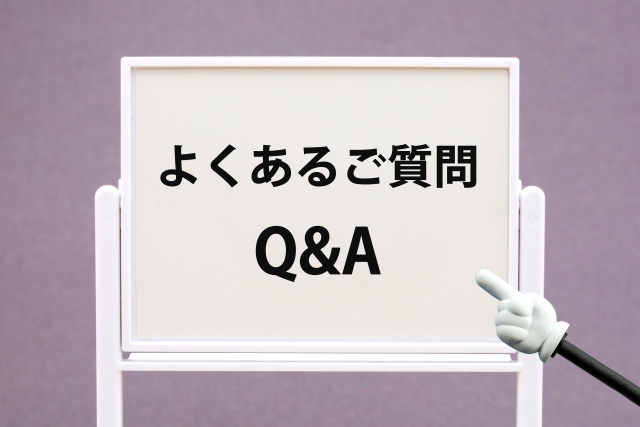
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) 令和6年3月15日 問18
Q.認知症高齢者の日常生活自立度の確認方法如何。
A.
・認知症高齢者の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見書を用いて、居宅サービス計画又は各サービスの計画に記載することとなる。なお、複数の判定結果がある場合には、最も新しい判定を用いる。
・医師の判定が無い場合は、「要介護認定等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知中「2(4)認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票(基本調査)」7の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いるものとする。
・これらについて、介護支援専門員はサービス担当者会議などを通じて、認知症高齢者の日常生活自立度も含めて情報を共有することとなる。
(注)指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について第二1(7)「「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について」、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について別紙1第二1(6) 「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について」の記載を確認すること。
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) 令和6年3月15日 問19
Q.認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を配置するとあるが、「配置」の考え方如何。常勤要件等はあるか。
A.
・専門的な研修を修了した者の配置については、常勤等の条件は無いが、認知症チームケアや認知症介護に関する研修の実施など、本加算制度の要件を満たすためには事業所内での業務を実施する必要があることから、加算対象事業所の職員であることが必要である。
・なお、本加算制度の対象となる事業所は、専門的な研修を修了した者の勤務する主たる事業所1か所のみである。
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) 令和6年3月15日 問20
Q.認知症専門ケア加算(Ⅱ)及び(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症加算(Ⅰ)の認知症介護指導者は、研修修了者であれば管理者でもかまわないか。
A.認知症介護指導者研修修了者であり、適切に事業所全体の認知症ケアの実施等を行っている場合であれば、その者の職務や資格等については問わない。
まとめ
本記事では認知症ケア加算について、単位数や算定要件、必要な研修などをご紹介しました。認知症の高齢者が増加すると予測されるため、今後益々認知症ケアの需要は高まります。そうした流れを受けて、介護現場では「認知症専門ケア加算」が導入され、専門研修を修了した職員がケアを提供する事業所に対し、1日3~4単位が加算されます。要件には利用者の割合や研修修了者の配置が含まれ、自治体への届出が必要です。加算取得により、職員のスキル向上、利用者の受け入れ促進、事業所の収益向上が期待されます。
認知症ケア加算を算定するにあたって、職員が認知症介護に係る研修を修了するまでには時間がかかります。算定を検討している事業所は算定要件をしっかり理解し、早めに準備に取り掛かりましょう。
